| �y �g�c���A�̖����y�ь�����𑽐����^�I����iPhone�A�v���u�g�c���A��^-���A�搶�̋���-�v �z |
 |
 |
|
 |
 |
|
|

| �����S�P�N�ɔ��s���ꂽ�u���{�y���{�l�@�Վ������@�g�c���A���W���v |
���G���ɂ́A���A�̖��̃C���^�r���[�L���̑��ɖ剺���E�쑺����T�؊�T�叫�����A�ɂ��Ċ�e���Ă��镶�͂ȂNj����[���L������R�f�ڂ���Ă���B�R�����̏o�ŎЁE�}�c�m���X�����蕜������Ă���A���݂ł����肷�邱�Ƃ��o����B
�剺���E�쑺���i�_�ސ쌧�߁A���M��b�A�����ږ⊯�Ȃǂ��C�A�����^������g�ܘY���������l���j�́A���̎G���̂Ȃ��Łu�g�c���A�搶�̐^���v�Ƃ����k�b���Ă���A���̒��Łu���A�搶�̎���b���ƌ����Ă��A�搶�̐^����悤�Ɍ�邱�Ƃ́A����ł��Ȃ����Ƃł���B�܂��āA�搶�̐��_�E�ʖڂ�l�ɒm�点�悤�ȂǂƂ������Ƃ͐�ɕs�\�Ƃ����Ă��悢�v�u�搶���܂��A�`�L���̑��̂��̂ɂ���ČȂ̐��_��m���邱�Ƃ͍D�܂ʂł��낤�B�ނ���A�����̎�ŏ������c�_�E���́E���́E���M�Ȃǂ̗ނɂ���Ď����̐��_�E�ʖڂ��f�i�Ƃ���邱�Ƃ����邾�낤�Ǝv����v�u�搶�̐��_�E�ʖڂ�m�낤�Ɨ~����Ȃ�A���̘b�������搶�̎����̋Ïk�Ƃ������ׂ��A�搶�̒����A�H���^�ȉ����n�ǂ��邱�Ƃ��K�v�ł���v�u�搶�́A�^�ɍ��Ƃ̎m�A���Ȃ킿���{���̎m�ł����āA��Ƃ��č����O���ɑ��ėJ�����̂ł���B���̌��ʂƂ��ċΉ���������Ɏ�������ŁA�Ή���肵�āA���Ƃ�J�����̂ł͂Ȃ��B���Ƃ��q�C�Y���̐l�ɂ��āA�������̐l�ł͂Ȃ������v�Ȃǂƌ���Ă���B
�܂��A�T�؊�T�́A�u�g�c���A�搶�̌O���v�Ƃ������͂̂Ȃ��ŁA�u���͒��ڏ��A�搶���A�������������Ƃ͂Ȃ��܂���ʉ��@��������Ȃ��������߁A�搶�̂��s�����̑��ɂ����Ă͂��܂葽�����ׂ����Ƃ������Ȃ����A���̋��P�A���̊����́A�ԐڂƂ͂����[�����̍����ɐZ�����āA�c����肱�̔N�Ɏ���܂ŁA�ݏZ����A��ɐ搶�̋��P�ɔw���Ȃ��悤���Ă���v�u���̎��搶�̌O���́A�F�ԐړI�ł��邪�A�ʖؐ搶�i���V�i�����A�̏f���j�Ƌʖؐ搶�̂��v�l����A�ꋓ�ꓮ�Ɏ���܂ŏ��A�搶��͔͂Ƃ��ČP�����ꂽ�̂ŁA���ɖY����Ȃ����̂���������B�Ȃ��ł��A���A�搶�͔��ɋΕƂł����������ŁA�ʖؐ搶�͏�Ɂg�Ў��Y�i���A�j�̔���������Α��v���h�ƌ����Ă����v�ȂǂƊ�e���Ă���B�T�́A���A�ɒ��ڊw�킯�ł͂Ȃ����A�����T���Y�ȂǂƓ��l�A���A�h���s���̋K�͂Ƃ��Ă���A�����I�Ȗ剺���Ƃ����Ă��悢���낤�B
|

���A�ɂ͂U�l�̌Z�햅�i�����A���A�A���A���q�A���a�q�A�q�O�Y�A���q�̏��j�������B�������m�ł��������Ɓi���A�̎��Ɓj�̐����͋ꂵ�����̂ł��������A�Ƒ����͂悭�A������������L���Ɉ�Ă�ꂽ�B���͏��A���Q�ΔN���̖��ł������B

| �g�c���A�̌Z�E�� �����i�~���Y�j |
���A���Q�ΔN��̌Z�E�����i�~���Y�j�B���A�Ɩ����́A�ƂĂ����̗ǂ��Z��ł������B�����́A�����S�R�N�W�W�Ŏ�������܂Ŗ����̐����������B

�e�e�����A�ƍł����Ă����Ƃ�����E�q�O�Y�B�q�O�Y�͐��܂�Ȃ���ɂ��Ď����s���R�ł������B����Ȓ�����A�͂����C�����Ă���A����⍖���������Ă��鏼�A�̎莆�����ʂ��₳��Ă���B

���A������L���Ɉ�Ă���E��q�B�u�e�v��������ɂ܂���e�S�@�����̂��ƂÂꉽ�ƕ������v�B�]�˂ōߐl�Ƃ��ď��Y�����܂������A�������̗��e�Ɉ��Ă��L���ȋ�ł��邪�A���A�̕�ɑ��鈤��ƂƂ��ɁA��E��q�̏��A�ɒ���������܂ł����`����Ă����ł���B

���s��w�����̋g�c���A���B
���̑��̊炪���O�̏��A�̊�Ɉ�Ԏ��Ă���Ƃ����Ă���B |

| �g�c���A�̒a���n�i���ƐՒn�j |
|

|
�����S�P�N���s�̎G���u���{�y���{�l�v�̗Վ������Ƃ��ċg�c���A�̓��W���g�܂�Ă���A���̂Ȃ��Ɂu���A�搶�̗ߖ���K�Ӂv�Ƒ肵�āA���A�̖��E���i�����V�V�j�ɁA���O�̏��A�ɂ��ăC���^�r���[�����L�����f�ڂ���Ă��܂��B���A�̐l�ƂȂ肪�`����Ă���A�ƂĂ������[���L���ł��B�����ł́A�u�Ƒ����猩���g�c���A�v�Ƒ肵�āA���G���̃C���^�r���[�L���̌�������f�ڂ��܂��i�ꕔ��������j�B
�y��コ��́u�V�O�]�N�O�̐̂��Â�A�����q���̎��ɋA��悤�ł��v�ƌ����āA�����̂��������ނ悤�ɘb���o���ꂽ�z
�@�w�Z�E���A�́A�c�����납��u�V�сv�Ƃ������Ƃ�m��Ȃ��悤�Ȏq���ł����B�����N����̎q�������ƈꏏ�ɂȂ��āA����������Ƃ��A�R�}���Ƃ��A�V�тɖ����ɂȂ������ƂȂǂ͂܂������Ȃ��A�����A���Ɍ������Ċ��Ђ�ǂ�ł��邩�A�M�������Ă��邩�ŁA����ȊO�̎p�́A���܂�v�������т܂���B�^���Ƃ��A�U���Ƃ��͂��Ă����̂��ƌ����܂��ƁA������ɂ߂ċH�ŁA���̋L���Ɏc���Ă�����̂͂���܂���B
�@�܂��A�u���q���v�Ƃ��u��K����v�Ƃ��ɒʂ��Ă����炸�A���i���S���V���j�ƁA�f���i�ʖؕ��V�i�j�ɂ��āA�w��ł��������ł����B���鎞���ɂ́A��������A�f���̏��ɒʂ��ċ������Ă��܂����B�f���̉Ƃ́A�킸�����S�����炢��������Ă��Ȃ������̂ŁA�O�x�̐H���̎��ɂ́A�ƂɋA���Ă���̂���ł����B
�@���̂���A���Z�̔~���Y�i�̂��̖����j�ƁA���A�́A����҂��A�܂����Ȃ�قǂɒ��̂悢�Z��ł����B�o������Ƃ����A�A��Ƃ����ꏏ�ŁA�Q��Ƃ��͈�̕z�c�ɓ���܂����A�H���̎��́A��̂��V�ŐH�ׂĂ���܂����B���܂ɕʂ̂��V�ŐH�����o���ƁA��̑V�ɕ��ׂ����Ă����قǂł����B
�@�e���`�ɓY���悤�ɁA���A�͒��Z�E�~���Y�ɂ��������A�~���Y�̌������ɋt�炤�悤�Ȃ��ƂȂǂ���܂���ł����B�~���Y�́A���A����Ώ�ŁA���́A���A���A��Ή��ł��B�����������ƂŁA�����܂藣��Ă��Ȃ������ł��傤���A�Z��̂Ȃ��ł��A�������O�l�́A�Ƃ��ɒ����悩�����̂ł��B�Z�E���A���S���Ȃ�O�́A�O�l���������Ɍ�荇���A��܂��������c���̂���̎v���o���A�����Ύ莆�ɏ����Ă��ꂽ���̂ł����x
�y���A�搶�͓Ǐ��̑��ɁA����Ƃ���������������A�܂��Ă���⏗���Ɏ���o���悤�Ȃ��Ƃ͑S���Ȃ������Ƃ����z
�@�w�Z�E���A�́A�D��Ŏ������ނƂ������Ƃ͂Ȃ��A�������z�킸�A�������ċޒ��Ȑl�ł����B�������m����ɂ��Ă�������̂��Ƃł��B������A��l�̂Ȃ��ɉ��ǂ��z�����������̂ŁA����𒍈ӂ��āA���ǂ������Ă���҂́A�����̑O�ɏo�����A���A�͂�������Ō���łȂ��A�V�䂩��݂邵�Ă������Ƃ�����܂��B
�@���Ƃ����͌��ɂ��Ȃ������̂ŁA�Â����́A�݂Ȃǂ��D�ނȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ������̂��A�Ƃ������Ƃł����A���ɂ́A�悭�킩��܂���B���ʂɇ����ꂪ�D�����������Ƃ������̂������Ăق����A�ƌ����Ă��A�v�������т܂���B�Z�́A������H���邱�Ƃ��A�����ʼn��߂Ă��܂����B�ł�����A���̐l�����̂悤�ɁA���ʂɁu�H��̉^���v�Ȃǂ�S�����Ȃ��Ă��A�݂��Q������A����ɂ߂��肷��悤�Ȃ��Ƃ́A����܂���ł����B
�@�Z�̐��U�͂킸���O�\�N�ŁA�Z���ƌ����A�������ɒZ�����U�Ȃ̂ł����A�O�\�ƌ����A���̂���̐��Ԉ�ʂ��炷��A�Ȃ��ނ����A�ƒ�����ׂ��N��ł����B����ǂ��A�Z�́A�N�ɂȂ��Ă���A�����ƑS���e�n�𗷂��Ă܂���Ă��܂������A���ɂ��鎞�́A����߂����g�̏�ŁA�ƂŋސT����悤�\�������Ă�����܂�������A�Ȃ����Ƃ����b�ȂǁA�ǂ�������o�Ă���͂�������܂���B�u�ߐl�Ƃ����g�̏ゾ����A�\�����́A�������ɍȂ�W��킯�ɂ͂����Ȃ����A���߂Đg�̉��̐��b�����鏗�����炢�́A�߂Â��Ă͂ǂ����v�ȂǂƁA�e�ʂɌ����Ă�����������悤�ł����A�e�ؐS����A���������Ă������������̂Ǝv���܂����A����́A�Z�̐S�̂�����m��Ȃ��l�̌��t�ł�����A���̂��Ƃ��Z�ɁA�ʂƌ������Č������҂͂��܂���ł����B�Z�́A���U�A�����ƊW�������Ƃ͂���܂���ł����x
�y���A�搶���c���̍��z
�@�w�Z���q���̂���A����f���̂��ƂŊw������Ă��܂������A�����������A�ɂ߂Č��i�Ȑl�ł����̂ŁA�����Ȏq���ɉ��������܂ł��Ȃ��Ă��A�Ǝv����悤�Ȃ��Ƃ��A��������܂����B��Ȃǂ́A���̗l�q�����Ō��Ă��āA�����͕�e�ł�����A����ɂ��̂тȂ����Ƃ��������悤�ŁA�u���������オ���āA�ǂ����֍s���Ă��܂��A����Ȃɂ炢�v�������Ȃ��Ă����ނ��̂��A�Ȃ��Ў��Y�i���A�̒ʏ́j�́A�����������Ă���̂��v�ƁA�͂��䂭�v�������Ƃ������������ł��B
�@���̂悤�ɌZ�́A�ƂĂ��]���ŁA������������ꂽ���Ƃ��A����ꂽ�Ƃ���ɂ��悤�Ȑl�ł����B����ǂ��납�A�u�����͌���ꂽ���Ƃ��A����ꂽ�Ƃ���ɁA�Ȃ��Ƃ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�ƁA���̂��Ƃ������A�����S�z���Ă���悤�ȁA����Ȑl�������̂ł��B
�@����ǂ��A�O���猩����A���̂悤�ɏ_�炩�ȌZ���A���ɂ́A�Ȃ��Ȃ������Ƃ��낪���������̂ƌ����܂��B�q���̂���̌Z��m���Ă���l�����́A�̂��Ɂu���N�̎�����A�r���ȂƂ��낪����������A����قǑ�_�Ȃ��Ƃ���Ă��̂ł��낤�v�ȂǂƁA��荇���Ă��܂����x
�y���A�搶�͋q��������̂��D�z
�@�w�Z�̊�ɂ́A�A�o�^������܂����B�������Ȃǂ�����Ȃ��悤�Ȑl�ł�������A�ꌩ����ƁA�ƂĂ������z�Ȑl�̂悤�Ɏv����̂ł����A��x�A��x�ƁA�b������@����������l�́A��l���q�����A�݂ȌZ��炤�悤�ɂȂ�A�Ȃ��āA�Z���A����ɉ����āA���b������悤�ɂ��Ă���܂����B�܂��A�D��ł��q�̑�������Ă���܂����B
���q�̍ہA���ю��ɂ́A�K�����т��o���悤�ɂ��Ă���܂������A���q���܂ɁA�������������̂��䖝�����Ȃ���A�b���Â���悤�Ȃ��Ƃ́A�����Ă������܂���ł����B�u�悢�������Ȃ�����v�ȂǂƂ������R�ŁA�H�����ɂȂ��Ă���̂ɐH�������߂Ȃ��A�ȂǂƂ������Ƃ͂���܂���ł����B
�@�Z�́A���肠�킹�̂��̂����ł����o�����āA�C�����悭�A���q���܂Ƃ�������ɁA�������ɂ���̂��y����ł���܂����B�Ƃ��ǂ��A������̕����琺�����������āA���q���܂��ĂԂ��Ƃ�����܂������A�Z�́A�������H�ו��������p�ӂ�������A�e���ȐH�ו��ł��A��������o�����Ƃ��D���ł����x
�y���A�搶�Ɋւ����b�z
�@�w�Z�́A�������d�邻�̎v�����A�q��ł͂���܂���ł����B�u�l�̂��߁A�l�̂��߁v�ƁA�����A����Ȃ��Ƃ����S�����Ă����悤�ł����B
�@�Z���u�l�̂��߁v���l���A����߂Đl�ɐe�ł������̂́A���Ԃ܂���Ă̓V���̂��̂������̂ł��傤�B�ѐ^�l�搶�̂���ɔ��܂荞��Ŋw������Ă������A����Ȏ�������܂����B
�@����ӁA�搶�̂���Ύ��ɂȂ�܂����B����ƌZ�́A���̉Ƃ̉ו����^�яo�����߂ɁA�����ɓ������̂ł����A�����̂��̂͐g�߂Ȃ��̂��������o���Ȃ������̂ł��B
�@�Ȃ��ɂ͑�ȋL�O�̕i���������悤�ł����A���ׂĂ��D�ɂ��Ă��܂��܂����B�Ō�́A�����Q������g�ɒ����Ă��邾���A�Ƃ������肳�܂����������ł��B
�@���ƂŁA����l���u�Ȃ��A����Ȃ��ƂɂȂ����̂��H�v�ƌZ�ɕ����������ł����A���̎��A�Z�͂��������������ł��B
�@�u���₵������Ƃ��\���Ă���l�́A�����ɂ��āA���낢��Ƒ�ȕi���������͂��ł��B�ł�����A��ł����������o�����Ƃ��܂����B���̏����i�̂悤�Ȃ��̂́A�Ȃ�قǎ��ɂƂ��Ă͑�Ȃ��̂ł����A�l���Ă݂�A�����������̂ł͂���܂���v
�@�Z���s�������Ƃ́A���ׂĂ����������q�Ȃ̂ł��x
�y�u���̂������v�Ɓu���̒m�点�v�z
�@�w�Z���A�u�e�v���@�S�ɂ܂���@�e�S�@�����̂��Ƃ���@���Ƃ������v�Ƃ����̂��r��Ŏ����������A���̖������A�܂����N���߂��Ȃ��Ă��܂����B�v���Ԃ��ƌ\�N���̂̂��ƂɂȂ�܂����A���̂���A�킽���̎��Ƃ́A���Ƃ��悤���Ȃ��قǁA�ߎS�ȏ�Ԃł����B
�@�Z�́A�����]�˂ɑ����āA���ɂ̂Ȃ��ɂ��܂����B���ꂾ���ł��A�J�T�Ȃ��Ƃł����̂ɁA���̂��뒷�j�̔~���Y�ƁA���A�̒�̕q�O�Y�́A������ׂāA�a�̏��ɂ������̂ł��B
�@��́A�Ў����q�O�Y�̂��𗣂ꂸ�A�����A�Ƒ��̊ŕa�Ŕ�ꂫ���Ă���܂����B���炭���ē�l�̕a���A������������Ɍ����������̂��Ƃł��B
�@��������A��ꂫ���Ă����̂ŁA�ŕa���Ȃ���A���̂��ʼn������Ƃ��Ă����̂ł����A�����ɖڂ��o�߂Ă��܂��܂����B�����āA��͕��ɁA�����\�����̂ł��B
�@�u���A�ƂĂ����Ȗ������܂����B�Ў��Y���A�ƂĂ��悢���F�ŁA�̂ɋ�B�̗V�w����A���Ă����������A�����ƌ��C�Ȏp�ŋA���Ă����̂ł��B�w����A���ꂵ�����ƁA���������Ɓx�Ɛ��������悤�Ƃ��܂�����A�ˑR�A�Ў��Y�̎p�͏����Ă��܂��A�ڂ��o�߂āA����Ŗ����Ƃ킩�����̂ł��v
�@���̎��A���͕�ɁA�����\���������ł��B
�@�u�������A�������Ă��Ė�������߂���B�Ȃ�����Ȃ��ƂɂȂ����̂��͂킩��Ȃ��̂�����ǁA���̂Ȃ��ŁA�����̎���a�藎�Ƃ���ĂˁB����Ȃ̂ɁA�ƂĂ��S�n���悩�����̂���B�w����a�藎�Ƃ����Ƃ����̂́A����Ȃɖ����Ȃ��Ƃ������̂��x�Ǝv���Ă�����v�ƁB
�@���̎��A���e�́A�������Ɋ�Ȗ����������̂��ƌ�荇���A�u������������Ў��Y�̐g�ɉ����������̂ł͂Ȃ����v�ƐS�z���������ł����A�u�܂����A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��낤�v�Ƃ��v�����悤�ł��B�������A���ꂩ���\�����܂�������āA�]�˂���g�������܂��B�Z���u�Y��̘I�Ə������v�Ƃ����ł����B
�@���̕��āA���e�͐���̖����v���o���܂����B�����āA�w��܂��Đ����Ă݂�A���������A�Z�̍Ŋ��̎����ƁA������������Ȃ����Ƃ��킩�����̂ł��B
�@��́A���ꂩ��A����ɐ̂̂��Ƃ��v���o���āA�����\���܂����B
�@�u�Ў��Y���A��R������]�˂ɑ����鎞�A�Y������Ȃ��܌���\�l���B��������ƂɋA�鋖�������āA�ƂɋA���Ă������Ƃ������B���̎��A���́A�Ў��Y�������g���Ă��镗�C��̂��ɁA�����ƍs���āA���̂悤�������Ȃ���A��l�����ŐS�̂�������荇���ĂˁB
�@���̎��A�����w������x�A�]�˂��炩�����Ă��āA�@���̂悢��������Ă������x�ƌ����ƁA�Ў��Y�́A�w���ꂳ��A����Ȃ��Ƃ́A���ł�����܂����B���́A�K�����C�Ȏp�ŋA���Ă��āA���ꂳ��́A���̂₳����������܂����ɂ��܂�����x�ƌ������̂�����ǁA�����ƓЎ��Y�́A���̎��̖��ʂ������Ƃ��āA���̖��̂Ȃ��ɓ����Ă��āA���F�̂悢��������Ă��ꂽ�̂��낤�ˁB�e�F�s�ȓЎ��Y�̂��Ƃ�����A�����ɈႢ�Ȃ��ƁA���͎v���Ă����v�ƁB
�@�����A��̖��������Ȃ�ɉ��߂��āA�����\���܂����B
�@�u���̂Ȃ��Ŏ����A����a���Ȃ���w�S�n�悢�x�Ɗ������̂́A�����炭�Ў��Y���Y��̘I�Ə����鎞�A�w�����ɂ͉����S�c��͂���܂���x�Ƃ������Ƃ��A���̓`�����������̂��낤�ȁv
�@�i�v�ɐ����ċA�邱�Ƃ̂Ȃ����H�̑����Ƃ��āA�Z�����̓����ɍs�����A���Ԃ�Z���g�́A�����Ăӂ����є��̒n�ނ��Ƃ͂ł��܂��A�Ɗo�債�Ă����Ǝv���܂��B����ǂ��A�������Ƒ��́A�Z�ɂ͉����߂��Ȃ����Ƃ�m���Ă���܂�������A���Ȃ炸������āA�A���Ă�����̂ƐM���Ă����̂ł��x
�y�Z�̏��ȏW�z
�@�w���̌Z�̎莆��O�ɂ���ƁA�͜��̔O�Ɋ������A���̎莆�ɂ��āA�l���܂ɂ��b������ƂȂ�ƁA���́A�ق�Ƃ��Ɋ�������悤�ȋC���ɂȂ�܂��B
�@�䗗����������A���킩��ɂȂ�܂��Ƃ���A���ʂ͏�ɖ����Ă��邾���ł͂Ȃ��A�������܂ŏ����Ă��������������Ǝv����قǂɁA�ׂ₩�Ȃ��Ƃ܂Œ��ӂ��Ă���Ă��܂��B����ɂ�������炸�A���́A�Z�̌���ɉ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��܂ܐ����Ă��āA���Ɛ\���Ă悢���킩��܂���B
�@���̂悤�ɌZ�̎莆��\��t���āA�{�ɂ��Ă���̂́A�Z���Ŋ����Ƃ������N�A���Z�̔~���Y���A���A����̎莆���o���o���ɂȂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ƐS�z���A���ӂ��Ă��ꂽ�̂ŁA�������Ă���̂ł��B���͂��̂��Ƃ��A���Ƃ��邲�ƂɁA���̎莆���J���ēǂ݁A���������߂Ă܂���܂����B
�@�ǂ�ł���ƁA�Z�̐[����ɐS����������A�����܂��ւ��邱�Ƃ��ł��܂���B�����ɂ��鎄�̖���A���̎o�́A�q���̂���A���̖{���ǂ�Ȃ��̂����킩��Ȃ��̂ŁA�u���́A���̖{���䗗�ɂȂ�ƁA�����������ɂȂ�܂��̂ˁv�ȂǂƁA���ɂ��̗܂̂킯���Ă������̂ł��B
�@���̑��ɁA�莆�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��ł����A�����瑗�����莆�̒[�����ɁA�Z���u���O�͂����������A����͂����������Ƃ���v�ȂǂƏ����Y���ĕԂ��Ă��ꂽ���̂��A��������܂����B���̂Ȃ��ŁA�Y����Ȃ����̂�����܂��B
�@�܂������A�����������̂ł��B
�@�u���Z���܂ɐ�������̂́A�͂����肵�Ă��܂��B�߂��Ȃ��̂ɍߐl�ɂ���邱�Ƃ͂������܂���B�ȂɂƂ��A���̂��S�̂قǂ��A��̕��X�ɑł������Ă�������A�����͂���āA�A����������҂����Ă���܂��v
�@����ƌZ�́A���̎莆�̗]���ɁA�����̎v�����Ƃ������Ă��ꂽ�̂ł��B
�@�Z���������݂����Ă��ꂽ���̎莆�́A�Z���]�˂ɑ�����O���A�ƂɋA���Ă������ɁA���ׂĎ����Ă��āA���ɓn���Ă���܂����B�����̎莆�́A�����Ȉ��o���ɓ���Ă������̂ł����A�����Ό��̊ԂɁA�ǂ����֍s���Ă��܂��܂����B���ɂȂ�ƁA�[���C�����ĕۑ����Ă����ׂ��ł������ƁA���₵���v���̂ł����A�����d��������܂���B
�@�Z�́A�������̎����������߂āA�u�S����������A��������ł����̂���B�n�����̂ɖL���Ȃ悤�Ɍ�����������A�j�ꂽ���̂������ɔj��Ă��Ȃ��悤�Ɍ��������悤�Ƃ����肷��悤�ȁA���������S�͂悭�Ȃ��B��������ҁA���������Ƃ�����A�悭�悭�S���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ���v�ƌ����Ă���܂����B
�@���ɂ́A���������Ă��ꂽ�Z�̐����A�������̒�ɋ����Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�܂���x
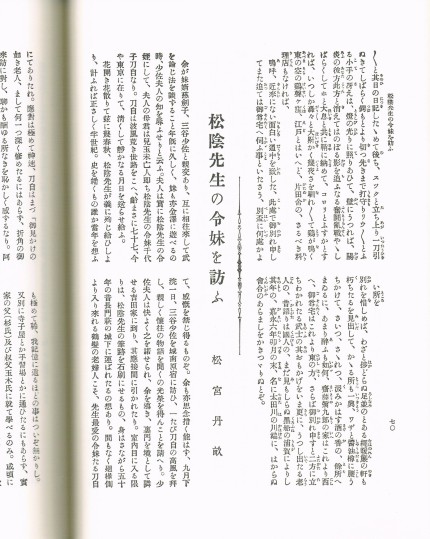
�u���{�y���{�l�@�Վ������@�g�c���A���W���v
�u���A�搶�̗ߖ���K�Ӂv�L�� |
|
|
|
| �y�Q�l�����z |
���[���A�g�c���A�Ƃ��̎����ς�m�肽������ |
|
|
- �����^�̍ŐV�ŁE�V���B�i������A�������^�j
- �u�����^�v�͂������A�u�����^�v�Ɏ���܂ł̏��A�̖剺����F�l�E���u�ɓ��Ă��莆�ȂǁA���A�̎����ς������ɂ��������𑽐��������^�B
- ��Ԓ�q�Ƃ���������q�d�V���A���A�̏��Y�������̎u���т��ېV���}�����쑺�a��ɒ��ڂ��A���A�Ƃ̊ւ����Ȗ��ɒ�����Ă���B
- ���A�̓�ΔN���̖��E���̋L������Ă���A �Ƒ��̊Ⴉ�猩���g�c���A�̎p�������яオ���Ă���B
- ���҂́A�c�{�ّ�w���w���������Y���C���B
- ���[���A�����^�A�g�c���A�̎����ς�m�肽�����ցB
|
|
